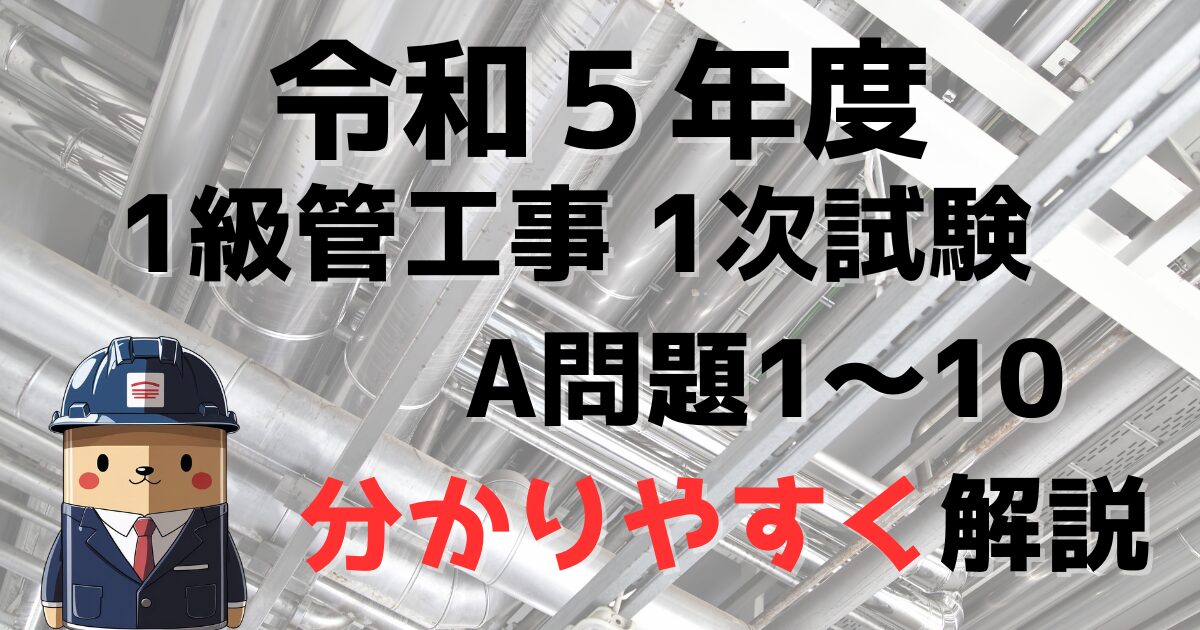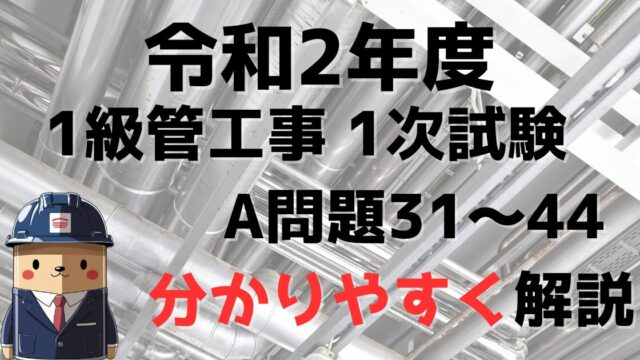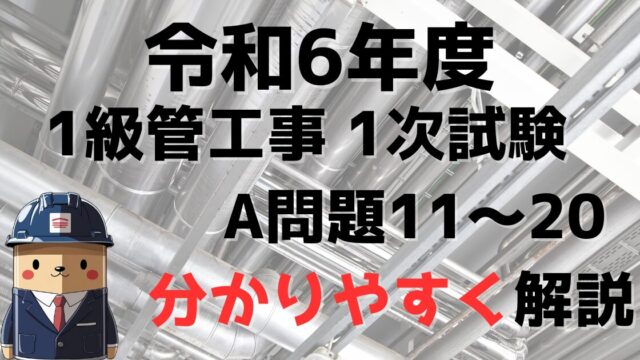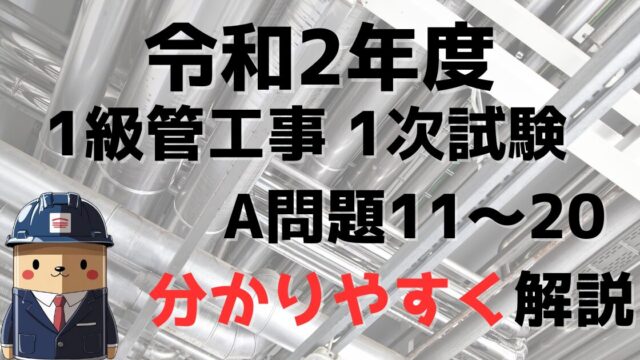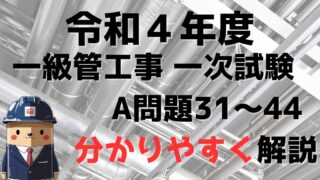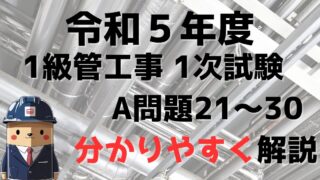問1
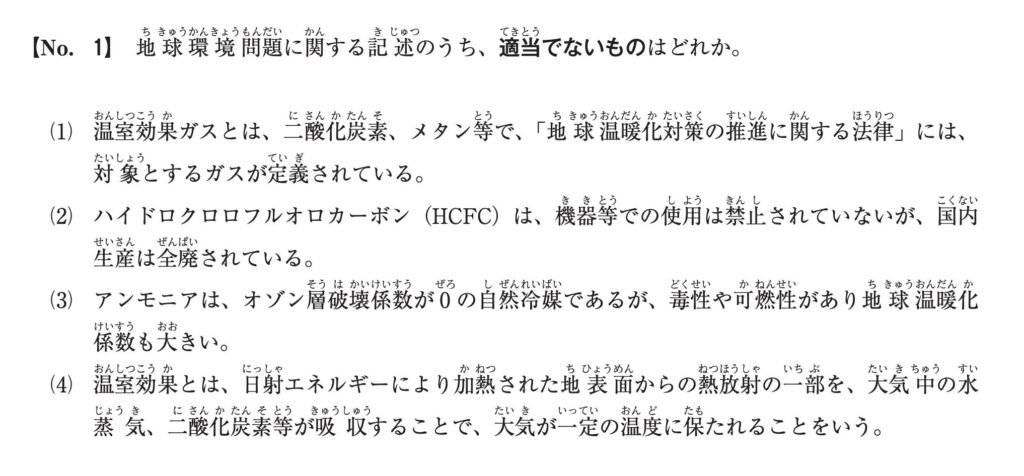
答えはここをタップ
3が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:温室効果ガスとは、二酸化炭素、メタン等で、「地球温暖化対策の推進に関する法律」には、対象とするガスが定義されている。
(2)の解説 ⭕️
問題:ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、機器等での使用は禁止されていないが、国内生産は全廃されている。
- ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)とは?
- フロンガス(CFC)を改良したもので、CFCよりもオゾン破壊が少ないガスとして使用されています。オゾン層破壊係数は少ないけどゼロではないので、2020年以降の新しい機器への使用は基本的にできません。
現在では、ハイドロフルオロカーボン(HFC)や自然冷媒(CO₂、アンモニア、プロパンなど)がオゾン破壊ゼロの冷媒として活用されています。
(3)の解説 ❌️
問題:アンモニアは、オゾン層破壊係数が0の自然冷媒であるが、毒性や可燃性があり地球温暖化係数も大きい。
「アンモニアの地球温暖化係数は小さい」が正解です。
アンモニアは自然冷媒であり、大気中に開放してもすぐ自然に消えます。人体に有害ではあるけれど、地球温暖化係数としては限りなく0に近いです。

ちなみに地球温暖化係数は、二酸化炭素を1としています!
(4)の解説 ⭕️
問題:温室効果とは、日射エネルギーにより加熱された地表面からの熱放射の一部を、大気中の水蒸気、二酸化炭素等が吸収することで、大気が一定の温度に保たれることをいう。
問2
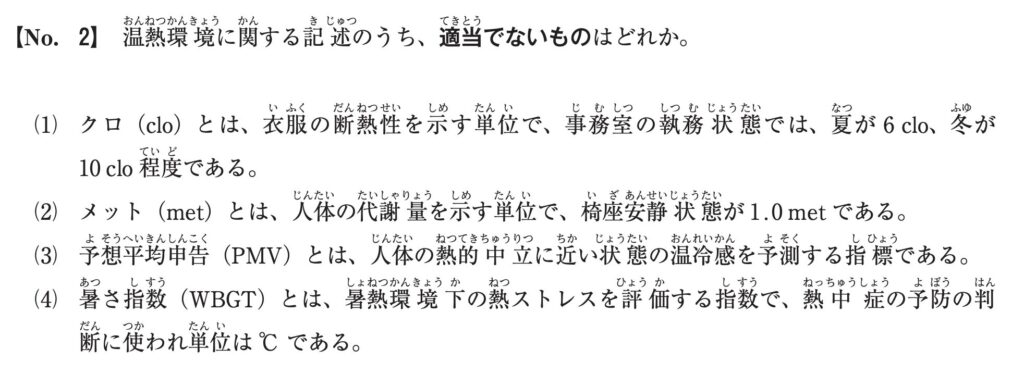
答えはここをタップ
1が間違い!
(1)の解説 ❌️
問題:クロ(clo)とは、衣服の断熱性を示す単位で、事務室の執務状態では、夏が6clo、冬が10clo程度である。
夏は0.6clo、冬は1.0cloが正解です。
cloの基準値
- 1clo:上下スーツ(シャツ+ジャケット+ズボン)を着ている状態
- 0clo:服を着ていない状態(裸)
- 0.5clo:軽装(半袖シャツ、薄手のズボンなど)
- 2clo:厚手のコートを着込んだ冬服

10cloと言ったら宇宙服レベルの断熱性能です!笑
(2)の解説 ⭕️
問題:メット(met)とは、人体の代謝量を示す単位で、椅座安静状態が1.0metである。
metの基準値
- 1 met:安静に座っている(事務作業、本を読むなど)
- 2 met:立って家事をする、料理など軽い活動
- 3〜4 met:ゆっくり歩く、軽い掃除
- 5〜6 met:速歩き、階段をのぼる
- 7〜8 met:ジョギング
- 10 met以上:激しい運動(ランニング、スポーツ競技など)
(3)の解説 ⭕️
問題:予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標である。
- 予想平均申告(PMV)とは?
- 「人が室内の環境をどのくらい暑い/寒いと感じるか」を数値化した指標です。
(4)の解説 ⭕️
問題:厚さ指数(WBGT)とは、暑熱環境下の熱ストレスを評価する指数で、熱中症の予防の判断に使われ単位は℃である。
問3
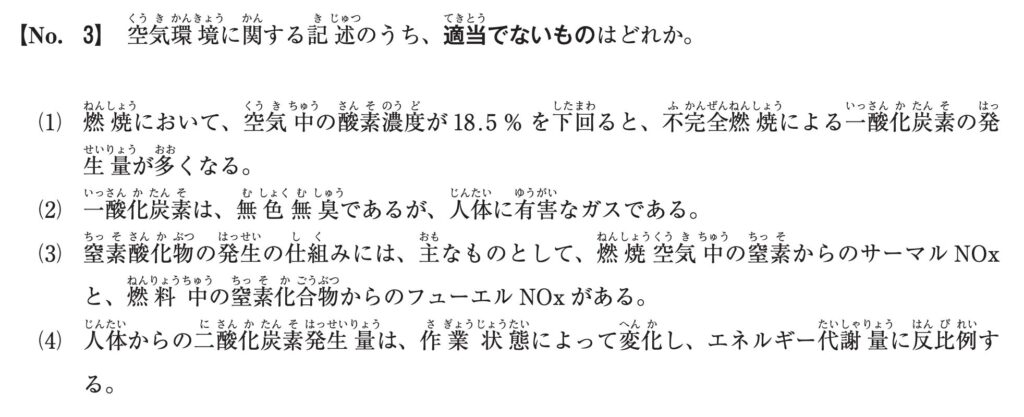
答えはここをタップ
4が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:燃焼において、空気中の酸素濃度が18.5%を下回ると、不完全燃焼による一酸化炭素の発生量が多くなる。

ちなみに通常の空気に含まれる酸素濃度は約21%です!
(2)の解説 ⭕️
問題:一酸化炭素は、無色無臭であるが、人体に有害なガスである。
(3)の解説 ⭕️
問題:窒素酸化物の発生の仕組みには、主なものとして、燃焼空気中の窒素からのサーマルNOxと、燃料中の窒素化合物からのフューエルNOxがある。
- サーマルNOxとは?
- 燃焼温度が1300℃を超えたあたりで、空気そのものが化学変化して窒素酸化物になったもの。
- フューエルNOxとは?
- 石油や重油などの燃料そのものに含まれている窒素分が燃えるときに窒素酸化物となったもの。
(4)の解説 ❌️
問題:人体からの二酸化炭素発生量は、作業状態によって変化し、エネルギー代謝量に反比例する。
エネルギー代謝量に「比例する」が正解です。
人体からの二酸化炭素は呼吸から発生しています。運動量が多くなれば呼吸も激しくなるので、エネルギー代謝量に比例するというわけです。
問4
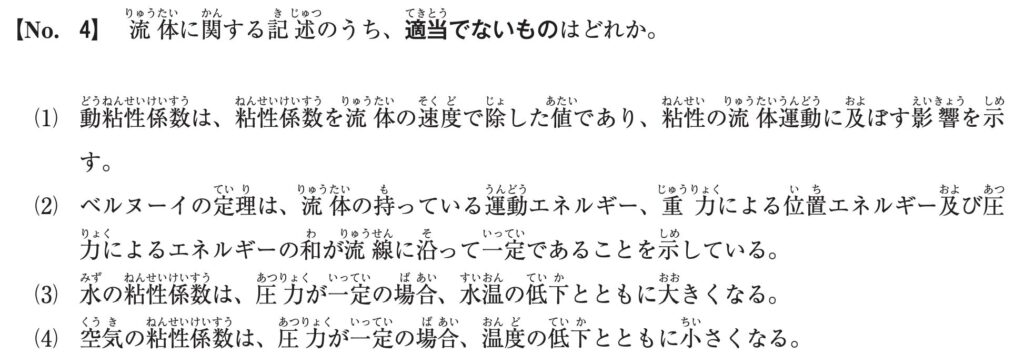
答えはここをタップ
1が間違い!
(1)の解説 ❌️
問題:動粘性係数は、粘性係数を流体の速度で除した値であり、年生の流体運動に及ぼす影響を示す。
動粘性係数は、粘性係数を流体の密度で除した値となります。
ν=μ/ρ
- ν(ニュー)=動粘性係数(単位:㎡/s)
- μ(ミュー)=粘性係数(単位:Pa・s)
- ρ(ロー)=流体の密度(単位:kg/㎥)
(2)の解説 ⭕️
問題:ベルヌーイの定理は、流体の持っている運動エネルギー、重力による位置エネルギー及び圧力によるエネルギーの和が流線に沿って一定であることを示している。
(3)の解説 ⭕️
問題:水の粘性係数は、圧力が一定の場合、水温の低下とともに大きくなる。
「粘性係数が大きい=流れにくい」という意味で、水温が低いほど分子の動きが鈍くなるので流れにくくなります。
(4)の解説 ⭕️
問題:空気の粘性係数は、圧力が一定の場合、温度の低下とともに小さくなる。
気体は分子がぶつかり合うことで「流れにくさ(粘性)」が発生します。温度が上がると分子の動きが活発になり、分子の衝突回数が増えて粘性が大きくなるわけです。
逆に温度が低くなるほど分子の動きが鈍くなるので、衝突回数が減り、粘性は小さくなります。
問5
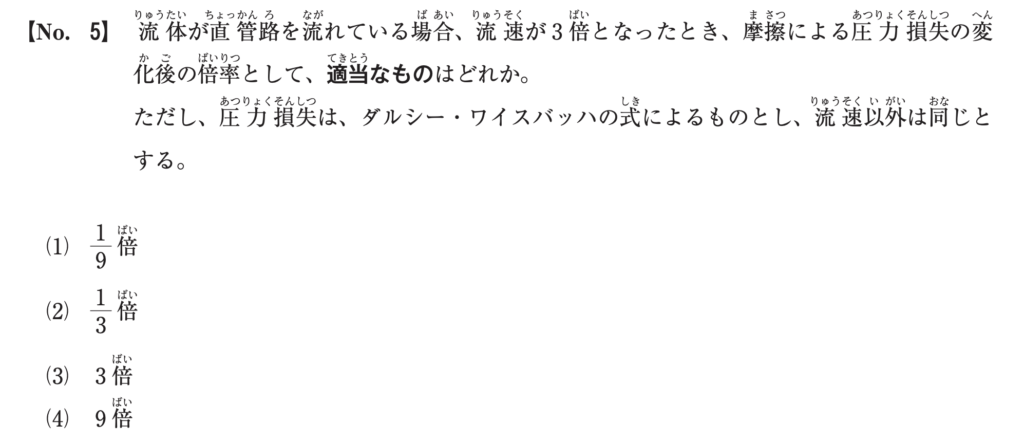
答えはここをタップ
4が正解!
ダルシー・ワイスバッハの式は以下のとおりです。
圧力損失(ΔP)=摩擦係数✕「管の長さ/管径」✕「密度✕速度²/2」
速度以外の条件が同じ場合、速度が3倍になると圧力損失の変化後の倍率は9倍になります。
問6
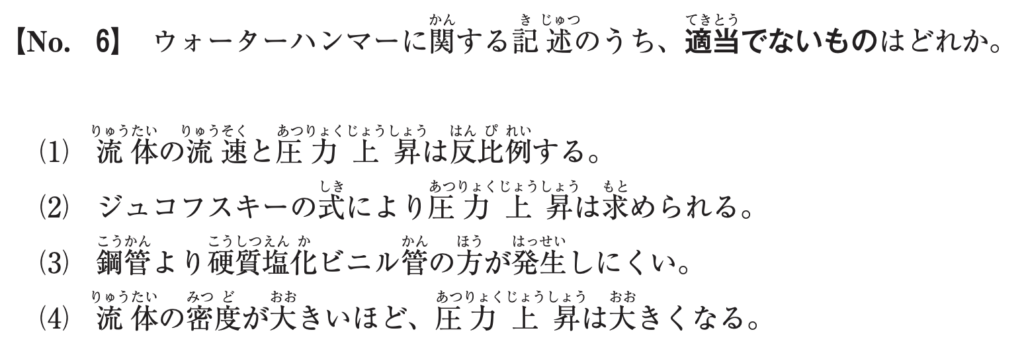
答えはここをタップ
1が間違い!
(1)の解説 ❌️
問題:流体の流速と圧力上昇は反比例する。
流体の流速と圧力上昇は比例します。
(2)の解説 ⭕️
問題:ジュコフスキーの式により圧力上昇は求められる。
(3)の解説 ⭕️
問題:鋼管より硬質塩化ビニル管の方が発生しにくい。
(4)の解説 ⭕️
問題:流体の密度が大きいほど、圧力上昇は大きくなる。
問7
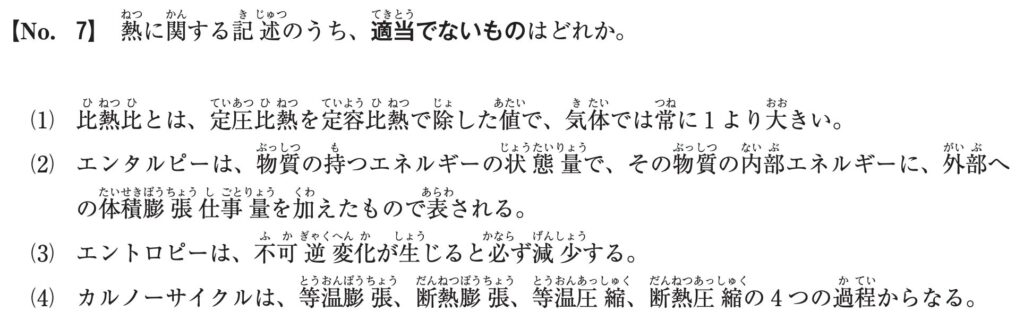
答えはここをタップ
3が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:比熱比とは、定圧比熱を定容比熱で除した値で、気体では常に1より大きい。
(2)の解説 ⭕️
問題:エンタルピーは、物質の持つエネルギーの状態量で、その物質の内部エネルギーに、外部への体積膨張仕事量を加えたもので表される。
(3)の解説 ❌️
問題:エントロピーは、不可逆変化が生じると必ず減少する。
エントロピーは、「不可逆変化が生じると必ず増加する」が正解です。
- エントロピーとは?
- 乱雑さ(ごちゃごちゃ具合)を表す量のことです。
- 不可逆変化とは?
- 自然に起きたら、外から特別な操作をしない限り元に戻せない変化のことです。
自然界ではエントロピーが減少することはありません。何かしらの変化が生じた場合、エントロピーは一定または増加します。
(4)の解説 ⭕️
問題:カルノーサイクルは、等温膨張、断熱膨張、等温圧縮、断熱圧縮の4つの過程からなる。
問8
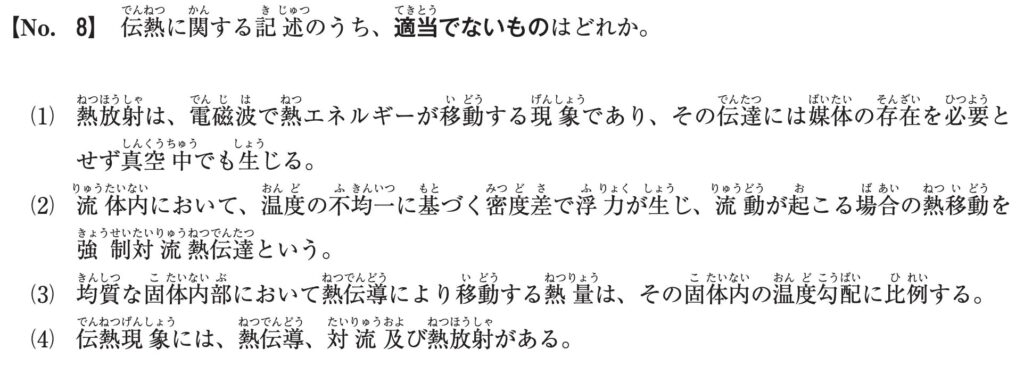
答えはここをタップ
2が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:熱放射は、電磁波で熱エネルギーが移動する現象であり、その伝達には媒体の存在を必要とせず真空中でも生じる。
(2)の解説 ❌️
問題:流体内において、温度の不均一に基づく密度差で浮力が生じ、流動が起こる場合の熱移動を強制対流熱伝達という。
温度の不均一に基づく密度差で浮力が生じ、流動が起こる場合の熱移動を自然対流熱伝達といいます。強制対流熱伝達はポンプやファンなどを使って、外部から強制的に力を加えて流体を流す方法です。
(3)の解説 ⭕️
問題:均質な個体内部において熱伝導により移動する熱量は、その個体内の温度勾配に比例する。

温度勾配は簡単にいうと温度差のことです!
(4)の解説 ⭕️
問題:伝熱現象には、熱伝導、対流及び熱放射がある。
問9
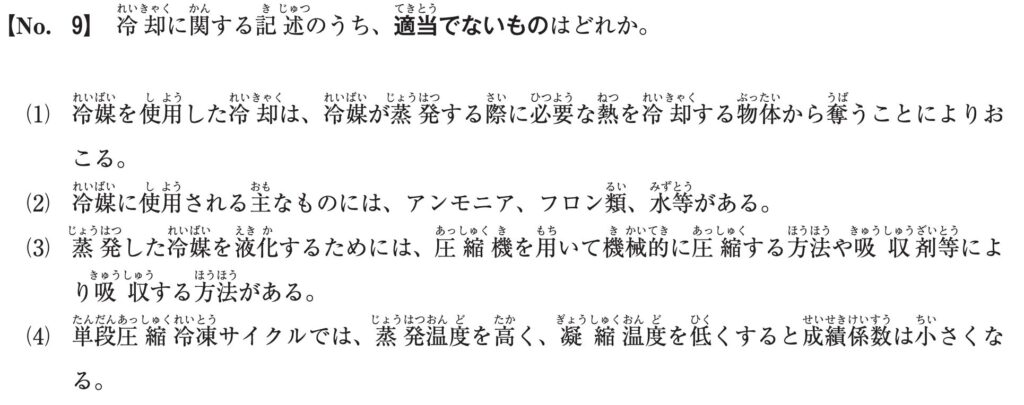
答えはここをタップ
4が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:冷媒を使用した冷却は、冷媒が蒸発する際に必要な熱を冷却する物体から奪うことによりおこる。
(2)の解説 ⭕️
問題:冷媒に使用される主なものには、アンモニア、フロン類、水等がある。
(3)の解説 ⭕️
問題:蒸発した冷媒を液化するためには、圧縮機を用いて機械的に圧縮する方法や吸収剤等により吸収する方法がある。
(4)の解説 ❌️
問題:単段圧縮冷凍サイクルでは、蒸発温度を高く、凝縮温度を低くすると成績係数は小さくなる。
「成績係数は高くなる」が正解です。成績係数とは、同じ電力でどれだけ効率良く冷やせるかを示しています。夏場のエアコンの例で考えてみましょう。
蒸発温度が高いパターン
- 設定温度が高い
- エアコンが無理しない
- 効率が良いってことになる
凝縮温度が低いパターン
- 外気温度が低い
- 冷媒の熱を捨てやすい
- 効率が良いってことになる
効率が良い=成績係数が大きいってことです。
問10
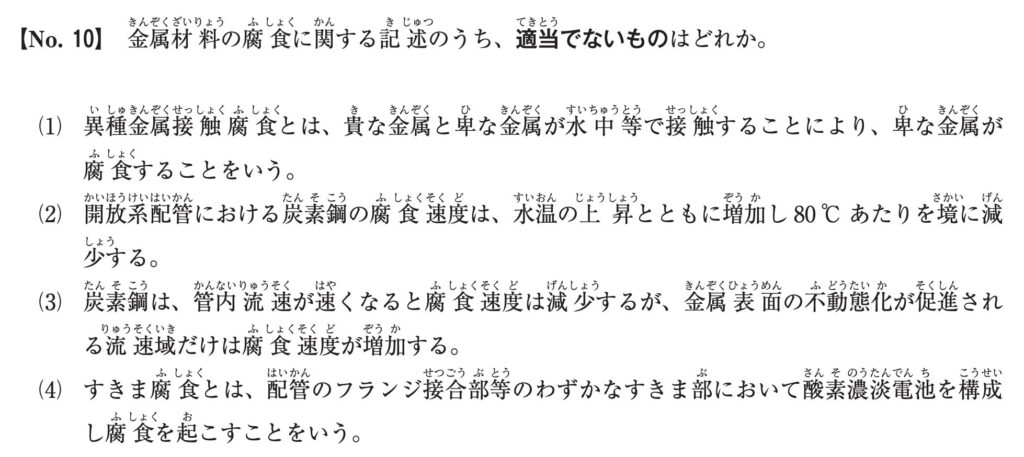
答えはここをタップ
3が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:異種金属接触腐食とは、貴な金属と卑な金属が水中等で接触することにより、卑な金属が腐食することをいう。
(2)の解説 ⭕️
問題:開放系配管における炭素鋼の腐食速度は、水温の上昇とともに増加し80℃あたりを境に減少する。
(3)の解説 ❌️
問題:炭素鋼は、管内流速が速くなると腐食速度は減少するが、金属表面の不動態化が促進される流速域だけは腐食速度が増加する。
- 不動態化とは?
- 金属の表面にごく薄い酸化被膜を作ることで、その金属が腐食しにくくなる状態、そのような処理を指します。
炭素鋼は錆びやすい材質です。流速が遅い場合、金属表面が不動態化によって錆びのような被膜ができ、新たな腐食を防ぐ効果があります。
しかし流速が速いと錆びの被膜が剥がれてしまい、腐食がどんどん広がってしまうわけです。
(4)の解説 ⭕️
問題:すきま腐食とは、配管のフランジ接合部等のわずかなすき間部において酸素濃淡電池を構成し腐食を起こすことをいう。