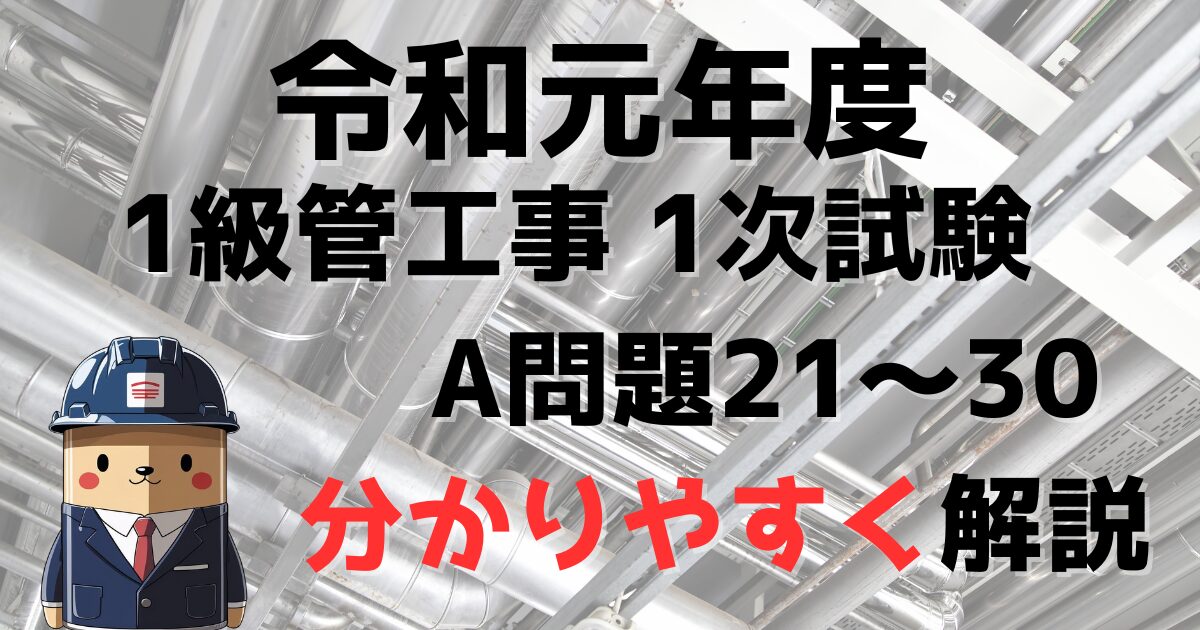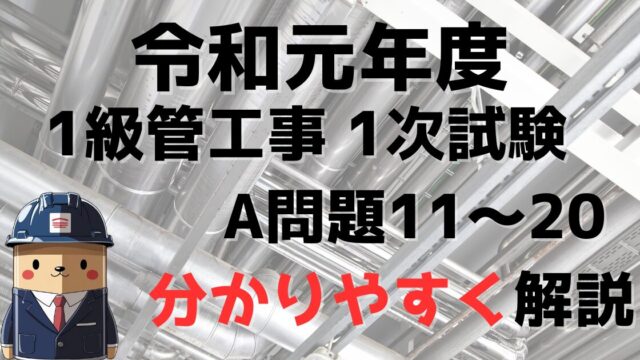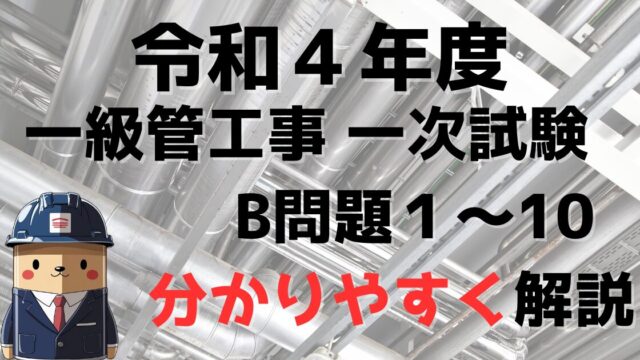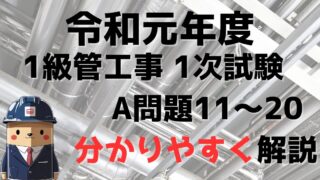問21 選択問題
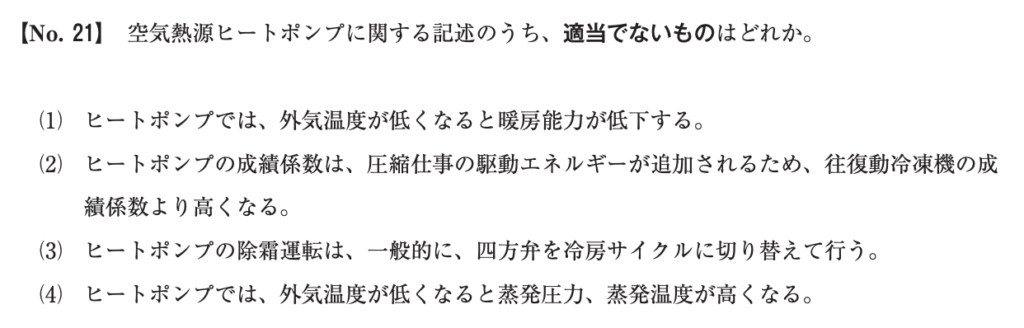
答えはここをタップ
4が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:ヒートポンプでは、外気温度が低くなると暖房能力が低下する。
(2)の解説 ⭕️
問題:ヒートポンプの成績係数は、圧縮仕事の駆動エネルギーが追加されるため、往復動冷凍機の成績係数より高くなる。
✏️用語の解説
(3)の解説 ⭕️
問題:ヒートポンプの除霜運転は、一般的に、四方弁を冷房サイクルに切り替えて行う。
✏️用語の解説
(4)の解説 ❌️
問題:ヒートポンプでは、外気温度が低くなると蒸発圧力、蒸発温度が高くなる。
✏️用語の解説
ヒートポンプでは外気温度より低い温度で蒸発させので、蒸発圧力・蒸発温度は低くなるのが正しいです。
問22 選択問題
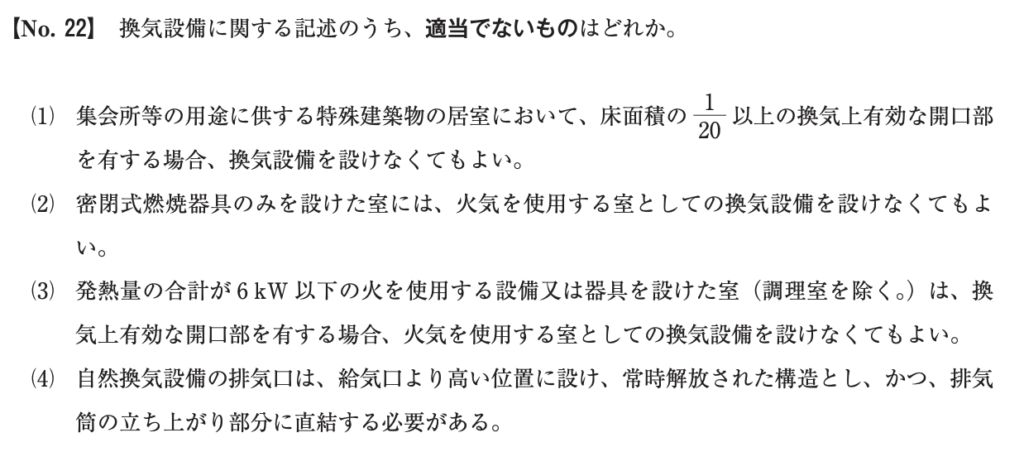
答えはここをタップ
1が間違い!
(1)の解説 ❌️
問題:集会所等の用途に供する特殊建築物の居室において、床面積の1/20以上の換気上有効な開口部を有する場合、換気設備を設けなくてもよい。
2003年のシックハウス対策改正(建築基準法改正)で、居室には原則として必ず換気設備を設けることが義務付けられています。「窓が十分にあるから機械換気はいらない」という考え方は、今は通用しません。
(2)の解説 ⭕️
問題:密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。
✏️用語の解説
(3)の解説 ⭕️
問題:発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)は、換気上有効な開口部を有する場合、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。
✏️用語の解説
(4)の解説 ⭕️
問題:自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。
✏️用語の解説
問23 選択問題
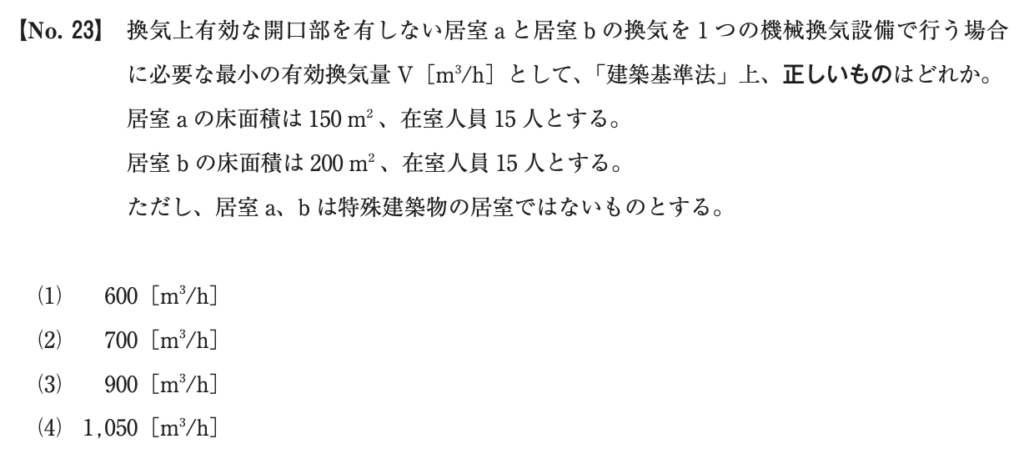
答えはここをタップ
2が正解!
問24 選択問題
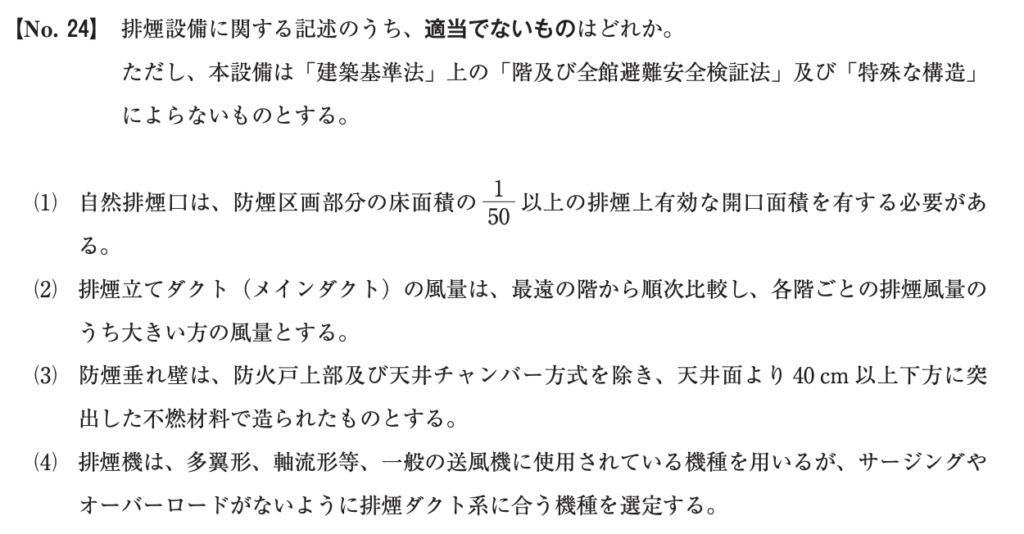
答えはここをタップ
3が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:自然排煙口は、防煙区画部分の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。
✏️用語の解説
(2)の解説 ⭕️
問題:排煙立てダクト(メインダクト)の風量は、最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい方の風量とする。
✏️用語の解説
(3)の解説 ❌️
問題:防煙垂れ壁は、防火戸上部及び天井チャンバー方式を除き、天井面より40cm以上下方に突出した不燃材料で造られたものとする。
防煙垂れ壁は、天井面より50cm以上下方に突出した不燃材料で造られたものが正解です。
(4)の解説 ⭕️
問題:排煙機は、多翼形、軸流形等、一般の送風機に使用されている機種を用いるが、サージングやオーバーロードがないように排煙ダクト系に合う機種を選定する。
✏️用語の解説
問25 選択問題
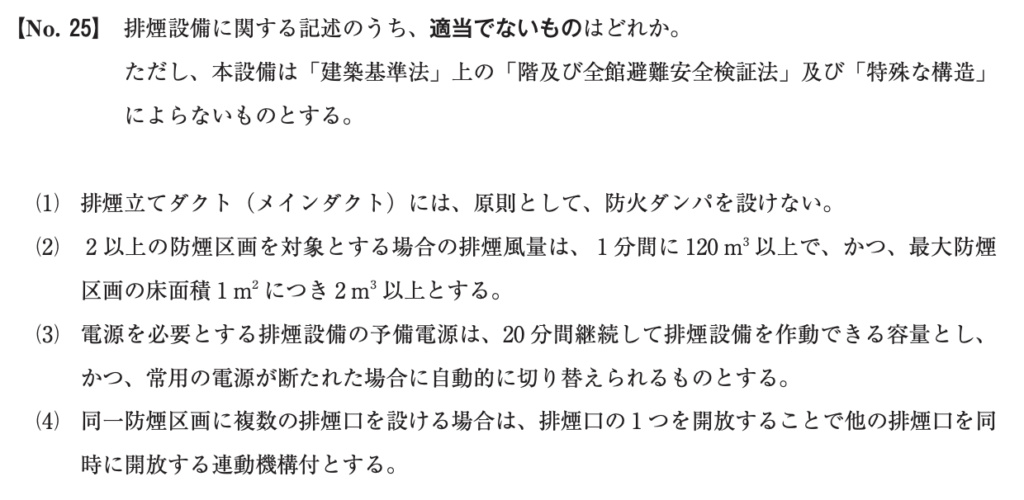
答えはここをタップ
3が間違い!
(1)の解説 ❌️
問題:排煙立てダクト(メインダクト)には、原則として、防火ダンパを設けない。
(2)の解説 ⭕️
問題:2以上の防煙区画を対象とする場合の排煙風量は、1分間に120㎥以上で、かつ、最大防煙区画の床面積1㎡につき2㎥以上とする。
✏️用語の解説
(3)の解説 ❌️
問題:電源を必要とする排煙設備の予備電源は、20分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるものとする。
30分間継続して排煙設備を作動できる容量とするのが正解です。
✏️用語の解説
(4)の解説 ⭕️
問題:同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、排煙口の1つを開放することで他の排煙口を同時に開放する連動機構付とする。
✏️用語の解説
問26 選択問題
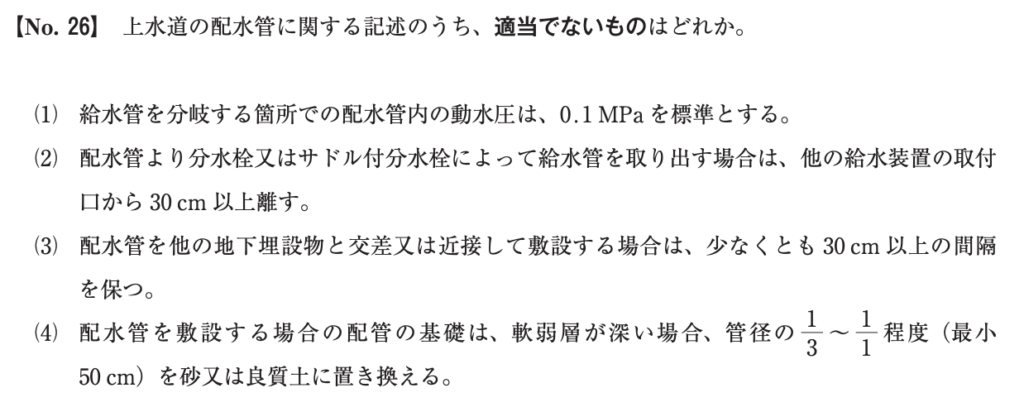
答えはここをタップ
1が間違い!
(1)の解説 ❌️
問題:給水管を分岐する箇所での配水管内の動水圧は、0.1MPaを標準とする。
✏️用語の解説
0.15〜0.2MPaが正解です。
(2)の解説 ⭕️
問題:配水管より分水栓又はサドル付分水栓によって給水管を取り出す場合は、他の給水装置の取付口から30cm以上離す。
✏️用語の解説
(3)の解説 ⭕️
問題:配水管を他の地下埋設物と交差又は近接して敷設する場合は、少なくとも30cm以上の間隔を保つ。
✏️用語の解説
(4)の解説 ⭕️
問題:配水管を敷設する場合の配管の基礎は、軟弱層が深い場合、管径の1/3〜1/1程度(最小50cm)を砂又は良質土に置き換える。
✏️用語の解説
問27 選択問題
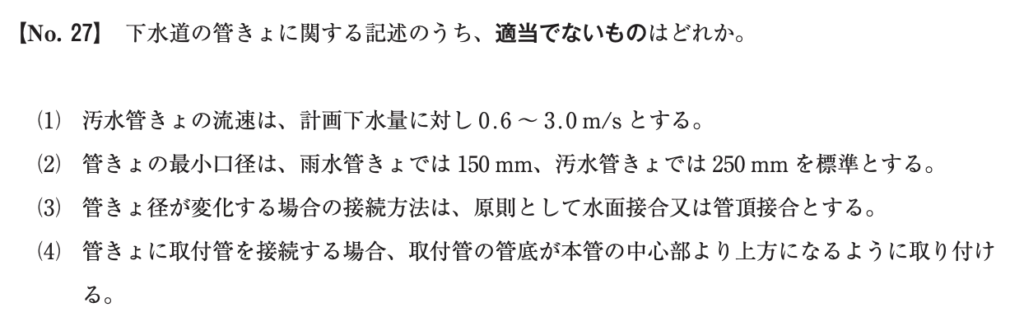
答えはここをタップ
2が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:汚水管きょの流速は、計画下水量に対し0.6〜3.0m/sとする。
✏️用語の解説
(2)の解説 ❌️
問題:管きょの最小口径は、雨水管きょでは150mm、汚水管きょでは250mmを標準とする。
✏️用語の解説
(3)の解説 ⭕️
問題:管きょ径が変化する場合の接続方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする。
✏️用語の解説
(4)の解説 ⭕️
問題:管きょに取付管を接続する場合、取付管の管底が本管の中心部より上方になるように取り付ける。
✏️用語の解説
問28 選択問題
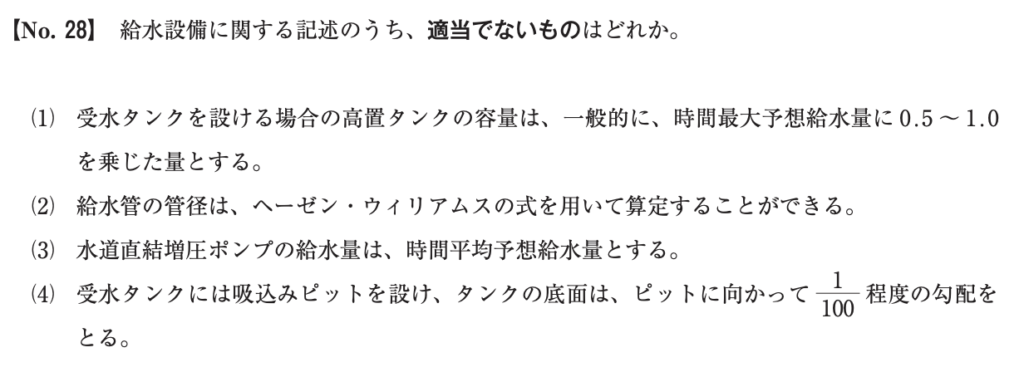
答えはここをタップ
3が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:受水タンクを設ける場合の高置タンクの容量は、一般的に、時間最大予想吸水量に0.5〜1.0を乗じた量とする。
✏️用語の解説
(2)の解説 ⭕️
問題:給水管の管径は、ヘーゼン・ウィリアムスの式を用いて算定することができる。
✏️用語の解説
(3)の解説 ❌️
問題:水道直結増圧ポンプの給水量は、時間平均予想給水量とする。
✏️用語の解説
時間最大予想給水量が正解です。
(4)の解説 ⭕️
問題:受水タンクには吸込みピットを設け、タンクの底面は、ピットに向かって1/100程度の勾配をとる。
✏️用語の解説
問29 選択問題
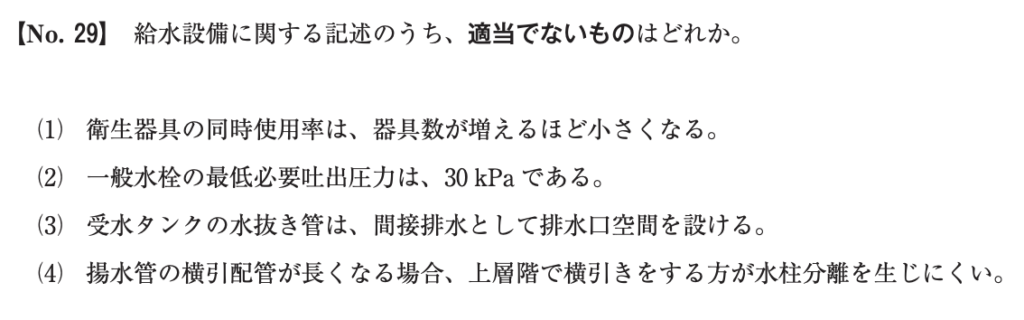
答えはここをタップ
4が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど小さくなる。
✏️用語の解説
(2)の解説 ⭕️
問題:一般水栓の最低必要吐出圧力は、30kPaである。
✏️用語の解説
(3)の解説 ⭕️
問題:受水タンクの水抜き管は、間接排水として排水口空間を設ける。
✏️用語の解説
(4)の解説 ❌️
問題:揚水管の横引配管が長くなる場合、下層階で横引きをする方が水柱分離を生じにくい。
✏️用語の解説
問30 選択問題
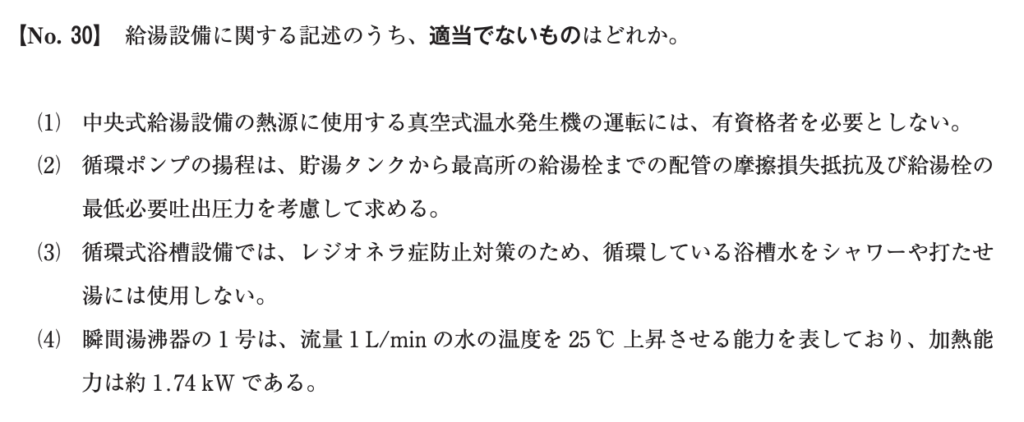
答えはここをタップ
2が間違い!
(1)の解説 ⭕️
問題:中央式給湯設備の熱源に使用する真空式温水発生機の運転には、有資格者を必要としない。
✏️用語の解説
(2)の解説 ❌️
問題:循環ポンプの揚程は、貯湯タンクから最高所の給湯栓までの配管の摩擦損失抵抗及び給湯栓の最低必要吐出圧力を考慮して求める。
✏️用語の解説
- 循環ポンプとは?
- お湯を往き管と還り管の配管ループ内でぐるぐる回して、蛇口を開けたときにすぐ温かいお湯が出るようにするポンプのことです。
- 揚程とは?
- ポンプが、水や液体をどれだけ高く押し上げられるかを示す力のことです。
問題文のかんたん解釈
「循環ポンプの揚程は配管の摩擦だけじゃなく、蛇口の必要水圧も含めて決めるんだよね?」という意味です。
循環ポンプタンクから出た水が最終的に同じタンクに戻るため、流体の高低差は打ち消し合い、純粋に配管やバルブ、継手などの摩擦損失のみが揚程選定の要素となるためです。
(3)の解説 ⭕️
問題:循環式浴槽設備では、レジオネラ症防止対策のため、循環している浴槽水をシャワーや打たせ湯には使用しない。
✏️用語の解説
(4)の解説 ⭕️
問題:瞬間湯沸器の1号は、流量1L/minの水の温度を25℃上昇させる脳力を表しており、加熱能力は約1.74kWである。